1980年代は「デジタル録音」の時代です。当時はレコード会社の広告でデジタル録音である旨が最大のセールスポイントとして大げさに扱われただけでなく、演奏の批評にも「デジロクにふさわしい表現」とか「デジタル時代ならではの名演」とか、いま読むとわけのわからぬフレーズが飛び交ったものでした。フィリップスによるコンセルトヘボウの最初のデジタル録音は、1979年9月に行われたエド・デ・ワールトとのセッションで、チャイコフスキーとワーグナーの2枚です。ところが翌10月のハイティンクによるチャイコフスキーのセッションは従来のアナログ録音で、11月のデイヴィスとのセッションでは5日のドヴォルザークがアナログで12日と13日のムソルグスキーがデジタル。このあたりは試行錯誤の時期だったのかもしれませんが、では1980年代以降はすべてデジタルかというと、1980年10月〜11月のセッションがアナログに戻っていたりして、もう少し過渡期は長かったようです。
ちなみに、日本でフィリップスのデジタル録音第一弾として発売されたのはジョン・ウィリアムス指揮ボストン・ポップスの「ポップス・イン・スペイス」で、1980年6月に録音され同年12月にすばやく発売されています。レコード番号は28PC-1で、2500円から新価格2800円への移行としても第一号だったようです。前述のデ・ワールトのチャイコフスキーは28PC-2として1981年3月に、デイヴィスのムソルグスキーは28PC-3として同年4月に、それぞれ国内盤が発売されています。確かにチャイコやムソ展よりも「ポップス・イン・スペイス」の方が「デジタル時代の幕開け」にはふさわしそうであり、録音が後なのに発売を先に持ってきた戦略もわかる気がします。

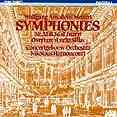 そのデジタル時代の1980年、コンセルトヘボウ管弦楽団はデッカとテルデックに登場。前者はアシュケナージ指揮のラフマニノフ(写真左)とハイティンク指揮のショスタコーヴィチ、後者はアーノンクール指揮のモーツァルト(写真右)です。このあたりでフィリップスとの専属関係が終わったのでしょうか。デッカはそれまでロンドン・フィルで進めていたハイティンクのショスタコーヴィチ全集録音をコンセルトヘボウ管弦楽団に切り替えましたし、テルデックはアーノンクール指揮でまとまった量の録音を現在に至るまで続けています。
そのデジタル時代の1980年、コンセルトヘボウ管弦楽団はデッカとテルデックに登場。前者はアシュケナージ指揮のラフマニノフ(写真左)とハイティンク指揮のショスタコーヴィチ、後者はアーノンクール指揮のモーツァルト(写真右)です。このあたりでフィリップスとの専属関係が終わったのでしょうか。デッカはそれまでロンドン・フィルで進めていたハイティンクのショスタコーヴィチ全集録音をコンセルトヘボウ管弦楽団に切り替えましたし、テルデックはアーノンクール指揮でまとまった量の録音を現在に至るまで続けています。
1981年には久々にコロンビア(ソニー)に登場。マイケル・ティルソン・トーマスによるアイヴスですが、クリティカル・エディションを使用した初録音とされるこのアイヴスのシリーズは、途中でオーケストラがシカゴ交響楽団にスイッチされました。ソニーではその他にハイティンクがマレイ・ペライアと組んでベートーヴェンのピアノ協奏曲全集を完成しています。

 このように他社録音が活発となった中で、フィリップスの1980年代はどのような展開を見せたのでしょうか。ドラティ指揮のバルトークやスメタナがある他は、デイヴィス指揮のハイドンのシリーズが目立ちますが、これは1986年1月に終了しています。そしてハイティンク。この時期の彼の大きな仕事はシューマンの交響曲全集でしたが、他にはブルックナーやマーラーを数曲再録音したものの、前者はウィーン・フィル、後者はベルリン・フィルとのプロジェクトが開始され、コンセルトヘボウ管弦楽団での新全集は企画されませんでした。あとはR.シュトラウスの録音がある程度で、1985年10月に開始され1987年12月に完了したベートーヴェンの交響曲全集をもって、ハイティンクとコンセルトヘボウ管弦楽団のフィリップス録音は終了してしまいます。そして翌1988年6月のセミヨン・ビシュコフによるR.シュトラウスの「ドン・ファン」の録音を最後に、フィリップスのコンセルトヘボウ録音そのものが長い休止に入ってしまうのです。「ドン・ファン」のカプリングとして翌年に「ツァラトゥストラかく語りき」が録音されたとき、オーケストラはフィルハーモニア管弦楽団になっていました。何があったのでしょうか。
このように他社録音が活発となった中で、フィリップスの1980年代はどのような展開を見せたのでしょうか。ドラティ指揮のバルトークやスメタナがある他は、デイヴィス指揮のハイドンのシリーズが目立ちますが、これは1986年1月に終了しています。そしてハイティンク。この時期の彼の大きな仕事はシューマンの交響曲全集でしたが、他にはブルックナーやマーラーを数曲再録音したものの、前者はウィーン・フィル、後者はベルリン・フィルとのプロジェクトが開始され、コンセルトヘボウ管弦楽団での新全集は企画されませんでした。あとはR.シュトラウスの録音がある程度で、1985年10月に開始され1987年12月に完了したベートーヴェンの交響曲全集をもって、ハイティンクとコンセルトヘボウ管弦楽団のフィリップス録音は終了してしまいます。そして翌1988年6月のセミヨン・ビシュコフによるR.シュトラウスの「ドン・ファン」の録音を最後に、フィリップスのコンセルトヘボウ録音そのものが長い休止に入ってしまうのです。「ドン・ファン」のカプリングとして翌年に「ツァラトゥストラかく語りき」が録音されたとき、オーケストラはフィルハーモニア管弦楽団になっていました。何があったのでしょうか。
理由の一つとしては、もちろんハイティンクからシャイーへの首席指揮者交替が考えられます。シャイーはデビュー当初フィリップスにも数枚の録音をしていたものの、基本的にはデッカの専属であり、コンセルトヘボウ管弦楽団もデッカへ比重を移したのでしょう。交替よりもひと足早く1986年に録音を開始したシャイーとコンセルトヘボウ管弦楽団の新コンビは、早くも1987年にはブラームス、1988年にはシューマンやブルックナーの一連の録音に着手し、同時にベリオ、シュトニケ、ワーナヘールといった新レパートリーも披露するなど、精力的な活動を展開していくのです。