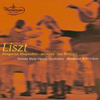 |
リスト
ヘルマン・シェルヘン指揮ウィーン・国立歌劇場管弦楽団 |
|
■ 作曲家リストのショーマンシップ |
|
|
これらの作品の元はと言えば、フランツ・リストがピアノの超絶技巧を前面に押し出して、自らの恣意的にも近いショーマンシップを貫徹するための自作のピアノ曲集から、自身が6曲選んで派手な効果を演出した管弦楽曲として、ドップラーの協力を得て編曲した、まさにショーマンシップのための作品集なのである。2枚目のディスクに収録された交響詩等の4曲にしても、元がピアノ曲であるものがやはり半数を占めており、基本的にはケバケバしいまでのショーマンシップ根性剥き出しの曲ばかりなのである。もちろん、だからこそ、一方でこれらの曲集が現代まで生き残ってきた証拠でもあり、かつそんなパフォーマンスが求められる傾向や欲求が、近年に至りむしろ増加しつつあるために、リストの音楽は徐々に復権しつつあると言えるのである。 |
|
|
■ 指揮者シェルヘンのショーマンシップ |
|
|
いつもは謎の多い指揮者であるが、ここでのリストの2枚組のディスクでは、シェルヘン特有の爆演スタイルを良い意味で貫徹しており、かつシェルヘンが意外にも同時に心底から楽しんで指揮をしている風景が眼前に浮かんでくるような、そんなシェルヘンの生一本なショーマンシップを味わえる珍しいディスクであるのだ。いつもの原曲を捻じ曲げるようなシェルヘンでも、まるでやる気の無さを誇示するようなシェルヘンでも、現代音楽の十字軍を自認していたシェルヘンでもない、まさにシェルヘンが垣間見せた、音楽を楽しむ目的のみの一途な演奏であり、シェルヘンならではのショーマンシップでもあるのである。 |
|
|
■ ウィーンのオーケストラのショーマンシップ |
|
|
どうやらオーケストラの実態は、ウィーン国立歌劇場のオーケストラではなく、ウィーン・フォルクスオーパーのオーケストラであると看做されているディスクではあるのだが、どっちみちウィーンのオーケストラであることに変わりはないのである。まぁ、しかし、いつもは「ハンガリー」と聴くと、途端に身構えて、顔を強張らせながら露骨に感情を剥き出しにする傾向の顕著なウィーンのオーケストラが、こんな風に好き勝手に楽しくパフォーマンスできるのなら、何の文句も言わずに喜んで弾くよ、という声が録音全体から聞こえてくるかのような、そんな尋常ではないオーケストラの乗り方なのである。 |
|
|
■ 聴き手の幸福感と、音楽の醍醐味 |
|
|
この演奏を聴いていて、勝手にリストの原作をあちこち改変しているので、何ともけしからん、非常にふざけたディスクだと立腹するような方がいたとしたら、ここではむしろ心から敬意を表したいと思う。ここまで、子どものようにあっけらかんと、人目も憚らず堂々と、指揮者もオーケストラも好き放題に、まさに聴き手の幸福追求のみを進んで提供するような潔い演奏を前にして、さすがの教条的な聴き手であっても、ここは苦笑いして、「まぁ、良いか。どのみち、この曲なんだから…」とか言いつつ、きっと容認することであろう。 |
|
|
■ ハンガリー狂詩曲(管弦楽版)について |
|
|
リストが作曲した同名のピアノ曲集(全19曲)から、6曲を選んで管弦楽曲に編曲したものである。管弦楽版で全6曲を演奏したディスクは意外に多く世に存在しており、名盤として有名なアンタル・ドラティのマーキュリーへの録音を始めとして、クルト・マズア、ズビン・メータ、イヴァン・フィッシャーの録音、その他が残されているし、あのカラヤンも折に触れて何曲かを継続して演奏してきたために、結果的に6曲中4曲の録音を残しているのだ。つまり、録音の機会も演奏の機会も、実は思いのほか多いのである。 |
|
|
■ 交響詩集について |
|
|
このディスクの2枚目は、交響詩集であり、有名な「前奏曲」、「マゼッパ」、「フン族の戦い」に加えて、原曲がピアノ曲であるメフィストワルツ第1番も演奏されている。基本的には、指揮者がショーマンシップに徹しているのは、ハンガリー狂詩曲集と同じなのだが、2枚目の冒頭に収録された最も有名な交響詩「前奏曲」は、意外なほど正面から真っ向勝負に挑んでおり、後半での加速振りはやや特殊ではあるものの、全体的なバランス等は非常にオーソドックスな名演奏となっているのである。その他の交響詩等も、非常に聴き映えのする好演奏ばかりである。 |
|
|
(2017年1月14日記す) |