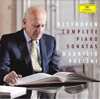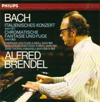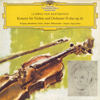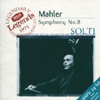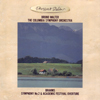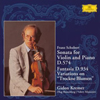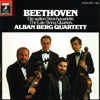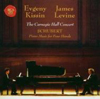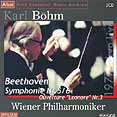CDを処分した際に手許に残したCDをこのところ一枚ずつ聴いています。今回はカール・ベームの1977年来日公演盤です。この演奏は当時中学生だった私がエアチェックして繰り返し聴いて内容をすっかり諳んじてしまったのに、なお、いや、それだからこそ処分できなかったCDの典型でした。不思議なことに、よく聴いた演奏であるのに今聴いてもまだまだ色褪せてきません。「レオノーレ」序曲第3番のフルートソロを耳にすると今更ながらすばらしいと思わずにはいられません。
この来日公演は私がクラシックを聴くことになったまさに原点です。引っ越しのために身を軽くし、いろいろなことを捨て去らなければならないのですが、これくらいを残したところで罰は当たらないと信じています。
なお、このCDについては、2002年5月19日の「What’s new?」でも触れていますね。引用するには若干長いのですが、以下に全文を転載しておきます。13年も前のことなのに、2002年の文章に付け加えるべきことが何もないことに我ながら驚いています。
2002年5月19日:すべてはここから始まった
ついにこんなCDが登場した。
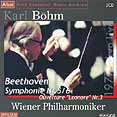
ベートーヴェン
交響曲第6番ヘ長調作品68「田園」
交響曲第5番ハ短調作品67
「レオノーレ」序曲第3番作品72b
カール・ベーム指揮ウィーンフィル
録音:1977年3月2日、NHKホールにおけるライブ
ALTUS(国内盤 ALT-026/7)
カール・ベーム最晩年の日本における人気は一体何だったのだろうか。まるで神様を崇め奉るようであった。・・・そんなことをいかにも訳知り顔で書く私だって、かつてはベームを神のように思っていたのであった。それもそのはず、私がクラシック音楽をまともに聴き始めたのは、このベーム指揮ウィーンフィルライブからなのである。当時私は中学3年生であった。
まだクラシック音楽になど興味のかけらもなかった私にウィーンフィルの話をやたらしたがる悪友のお陰で、私は1977年のベーム来日演奏をFMで聴かされたのだ。それもテープにまで収録しながら。ベートーヴェンの「運命」も、「田園」も、「レオノーレ」序曲もそれまで聴いたことがなかった。ベームのこの日の指揮で初めて聴いたのである。なぜか私はクラシック音楽がそのまま好きになり、テープに収録したテープを何回も聞き返した。テレビで放映された来日公演の模様も一所懸命見た。ついには、メロディーや演奏の間合いをすべて諳んじてしまった。
もし、この時私がベームの演奏に耳を傾けていなければ、今私はクラシック音楽を聴いていなかった確率が高い。どうしてそのままクラシック音楽を聴き続ける気になったのか不思議ではあるのだが、「カール・ベーム」という、当時最大級のブランドを頼りにクラシック音楽を追い求めていったわけだから、私にとって、最も重要な指揮者である。私がかなりドイツ・オーストリアものの、しかもオーケストラ曲を中心に音楽鑑賞をするようになっているのも、この人との出会いがなせる技なのだろう。
その後、私は最晩年のカール・ベームを高くは評価しないようになった。他の指揮者の演奏を数多く聴くにつれ、神とは崇めなくなった。最晩年のあの人気は過熱しており、異常であったと分かるようになった。最近では、「オペラはともかく、シンフォニーはどうもなあ...」などと宣う始末である。
しかし、このCDを改めて聴いてみると、カール・ベームはやはり立派なものだったのだと思う。ライブにつきものの乱れはあるものの、収録された3曲は実に見事な演奏で、私ははるか25年前の自分に戻って、かつての感動を追体験させられた。もしかしたらあの「運命」は駄演なのかもしれないが、私が初めて繰り返し繰り返し聴いた演奏だけに身体があの演奏に反応してしまう。「レオノーレ」序曲に登場する、天から舞い降りてくるように聞こえるフルートなど、今なお強く私を引きつけてやまない。「田園」を聴くと、宇野功芳氏が熱に浮かされたような賛辞を送っているのが頷ける。魅惑的なホルンセクション。ウィーンフィルがあのNHKホールでこのような鳴り方をしていたとは、驚きである。
今さら昔聴いていた演奏をCDで聴いても仕方がないかな、と思いつつこのCDを買ったが、25年の時を隔てても同じ感動が甦ってくるとは! 私の場合、すべてはこの演奏から始まっている。今にして思えば、クラシック音楽という豊饒の世界を私に直接に伝えたカール・ベームは私の大恩人である。ゆめゆめ疎略に扱ってはいけないと肝に銘じた次第。
(2015年2月28日)