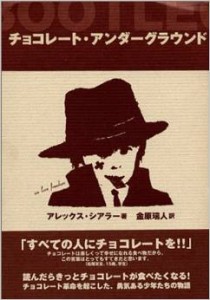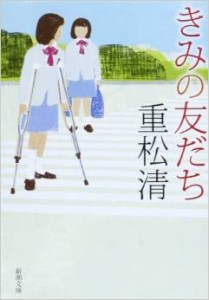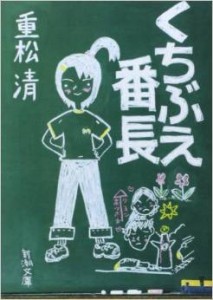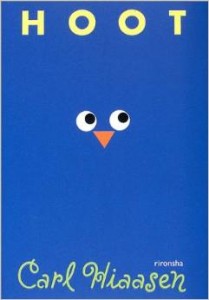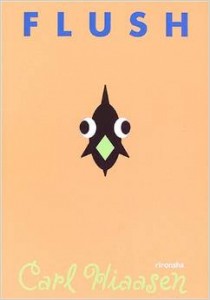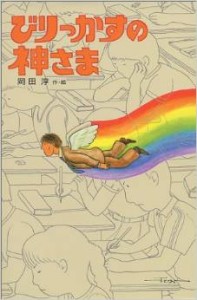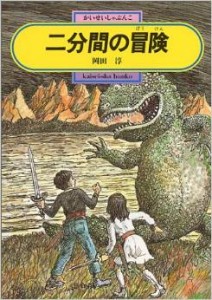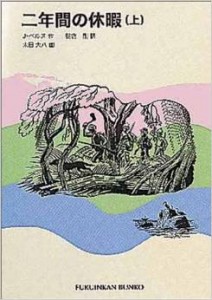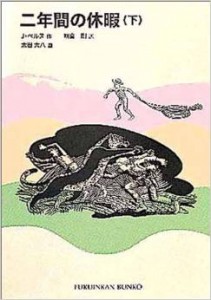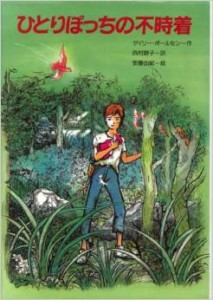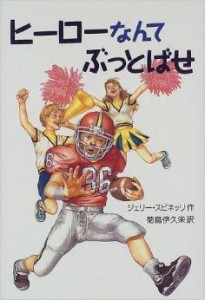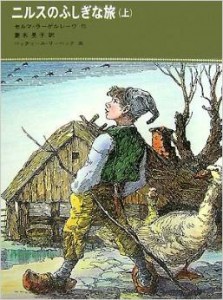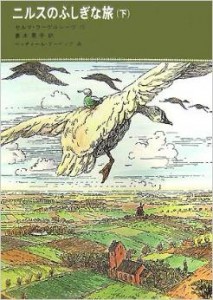『チョコレート・アンダーグラウンド』
原題”Bootleg”
2003年作品
アレックス・シアラー著
金原瑞人訳
求龍堂
本はパッケージ商品であると私は考えています。本には人が長い間培ってきたノウハウが集約されているからです。本の大きさ、紙の質、字体、余白、カバーや帯のデザインなど、どれひとつとして安易に作られていません。
その点でもこの『チョコレート・アンダーグラウンド』は出色です。日本語タイトルが示すとおり、これはチョコレートに関する話ですが、本の表紙からしてチョコレート色です。カバーを外すと、本体もチョコレート色。さらに、本文はおろかすべての文字がチョコレート色になっています。こういう本には出版社の愛が感じられます。
内容はユーモラスでもあり、シリアスでもあります。ある国で選挙が行われます。そのとき、健全健康党が自由愛好党に勝ってしまう。主人公の父を含め、多くの人が投票にさえ行きませんでした。多分、健全健康党には組織票でもあったため、投票率が低ければ有利になったのでしょう。選挙で勝利した健全健康党は、世界の秩序を少しばかり正し、世界を住みやすくするだけだと考えられていたのに、政権を掌握するとチョコレート禁止令を発しました。健全健康党は民主的に選ばれた独裁政権になってしまうのです。ばかばかしい設定とも考えられるのですが、選挙の実態を知っている大人が読めばあり得ることだと思わざるを得ません。この点は仮想現実として秀逸です。ただし、それは大人の読み方ですね。子どもは物語の展開を理屈抜きで楽しめるはずです。物語では主人公たちが、禁止されたチョコレートを地下バーで広め、やがて政権を追い詰めます。
子どもは、この本を手渡すと、500ページもある本なのでそのずっしりとした重みにちょっとひるみます。しかし、チョコレート色で作られた本の体裁を教え、1ページの文字数も抑えられ、読みやすく組まれたページを見せると安心して読み始めます。漢字の読みがながやや少ないので、小学4年生には読書力がある場合に、普通は小5からお薦めです。
(2015年2月28日)