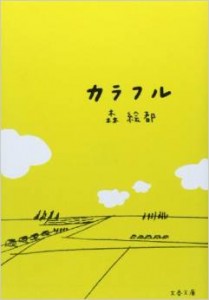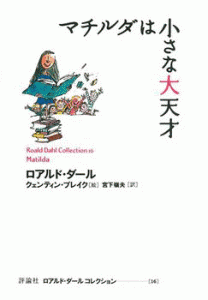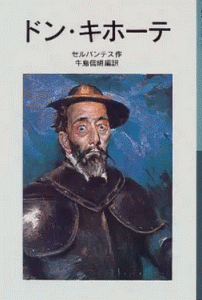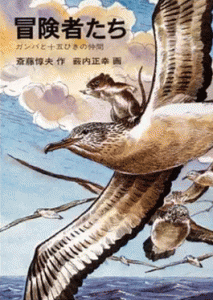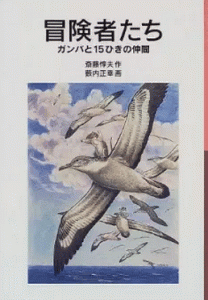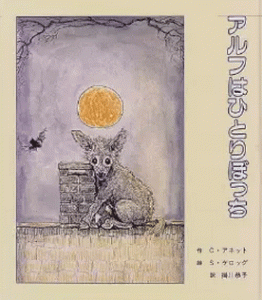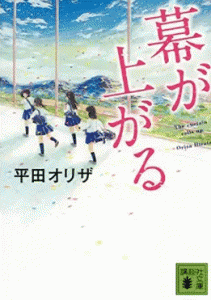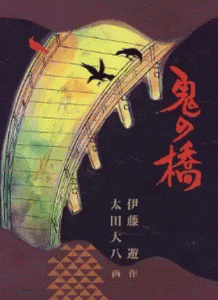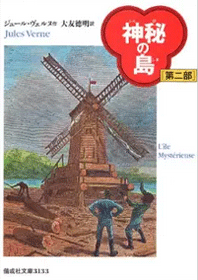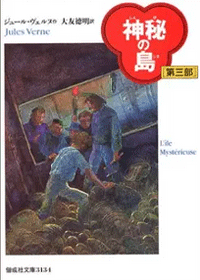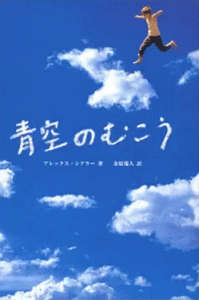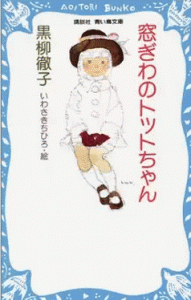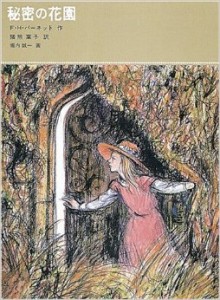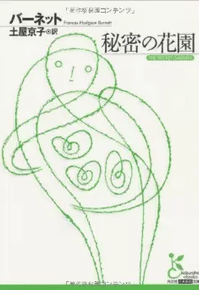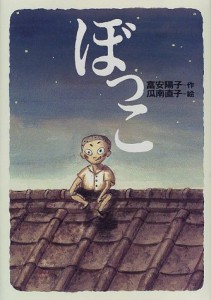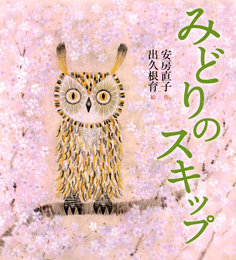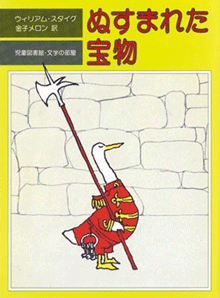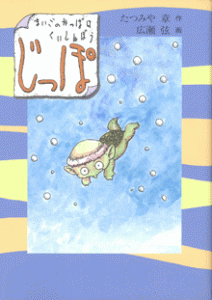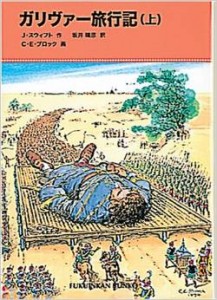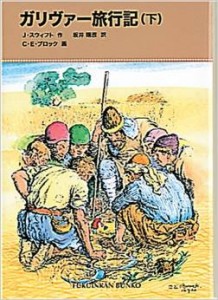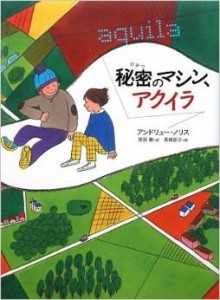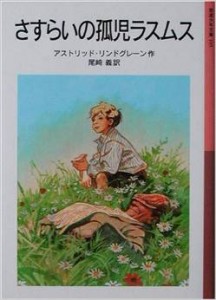『カラフル』
1998年作品
森絵都著
理論社
主人公の「ぼく」の魂があの世に向かって漂っていると、天使に呼び止められ、「あなたは抽選に当たった」と訳の分からないことを言われます。「ぼく」は現世である大きな過ちを起こしたらしい。そういう人は輪廻のサイクルから除外され、二度と生き返ることができません。しかし、下界に戻って修行をすれば輪廻のサイクルに入れてもらえると天使は言います。そうして「ぼく」は現世で14歳の少年小林真の身体を借りて修行を始めます。さて、「ぼく」の犯した大きな罪とは何なのでしょうか?
結論から言いますと、「ぼく」の正体は、他ならぬ小林真自身で、犯した罪とは自殺でした。小林真の家庭環境、友人関係が明らかになるにつれて、彼が自殺したくなるのも分からないではありませんが、自殺は間違いなく大きな罪なのです。「ぼく」は下界で自分の生きる世界を見つめ直し、もがきます。そして最後に、人間のいる世界で生きていくことを決意します。そこは目も眩むほどカラフルな世界です。彼の修行はそこで終わり、力強く生きていくのです。
死について考えることは、生について考えるのと表裏一体です。この作品はその両面からアプローチし、生きることの意味を伝えています。森絵都の代表作であり、傑作の誉れ高いのも頷けます。
この作品の文章は平易ですので、読もうと思えば小学5、6年生から読めます。しかし、作品理解のためには精神的に大人になってくる中学生以降が良いでしょう。小林真の母親は不倫をしていますし、彼の意中の女子中学生は平然と援助交際をして荒稼ぎをしています。こうした部分は小学生には刺激が強すぎますし、場合によってはその重大な意味を理解されない可能性もあります。子どもに読ませる場合はお母様ご自身の目で確認なさってからの方が良いでしょう。
(2015年3月23日)