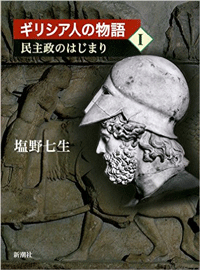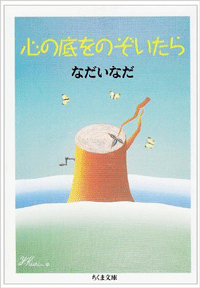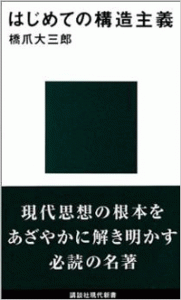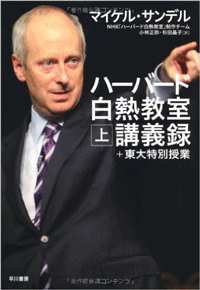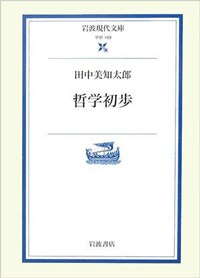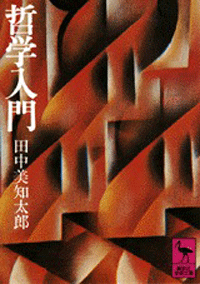塩野七生の『ギリシア人の物語 Ⅰ 民主制のはじまり』(新潮社)を読む。
これは私にとって待望の本だった。ギリシアが当時の超大国ペルシアに勝てたのはなぜなのだろうか、という疑問がずっとあったからだ。私は塩野七生の大ファンなので、ギリシャを取り上げた本をぜひ書いてもらいたいとかねてから願っていた。しかし、塩野七生は15冊に及ぶ『ローマ人の物語』の後、十字軍の時代まで書き上げている。さすがにもうギリシャ時代に戻ることはないのではと私は半ば諦めていたのである。だから、この本が出版されると知った時は欣喜雀躍した。塩野が私のために書いてくれたのではないかとさえ思っている。
それはともかく。
この戦役についての個別情報なら私だって少しは知っている。
BC490 (第一次ペルシア戦役)
- アテネが主力のギリシア軍、マラトンでペルシア軍を撃破。
BC480 (第二次ペルシア戦役)
- スパルタ軍、テルモピュレーでペルシア軍相手に玉砕。
- アテネを主力とするギリシャ軍、サラミスの海戦にてペルシャ軍を撃破。
BC479
- スパルタを主力とするギリシア軍、プラタイアでペルシア軍を撃破。
テルモピュレーの戦いは戦史マニアには著名だ。スパルタの王レオニダスがわずか300の兵でペルシアの大軍を迎え撃った戦いである。この模様は近年の映画『300』でもドラマチックに描かれている(激突シーンはこちら)。また、マラトンの戦いもサラミスの海戦も『300』の続編『帝国の進撃』で取り上げられていた。しかし、映画を観たところで、ペルシア戦役の全体像が掴めるわけではない。映画は絵になるところしか扱わないし、脚色が激しすぎ、支離滅裂になる場合もあるからだ。実際に、『300』と『帝国の進撃』にはあり得ないと思われるシーンが続出する。
『ギリシア人の物語』は違う。塩野はアテネやスパルタの政体、ギリシャの状況を描きながら、迫り来るペルシアの脅威に対してギリシアの人々がどのような考えのもと、どのような行動を取っていったのかを克明に示している。これなら、ギリシア勝利の理由はよく分かる。
塩野はギリシャの勝利について以下のようにまとめている。
**************************************************************
ペルシア(東方)は、「量」で圧倒するやり方で攻め込んできた。それをギリシア’(西方)は、「質」で迎え撃ったのである。
「質」といってもそれは、個々人の素質というより、市民全員の持つ資質まで活用しての、総合的な質(クオリティ)、を意味する。つまり、集めて活用する能力、と言ってもよい。
これによって、ギリシアは勝ったのである。ひとにぎりの小麦なのに、大帝国相手に勝ったのだった。
この、持てる力すべての活用を重要視する精神がペルシア戦役を機にギリシア人の心に生まれ、ギリシア文明が後のヨーロッパの母体になっていく道程を経て、ヨーロッパ精神を形成する重要な一要素になったのではないだろうか。
この想像が的を突いているとすれば、今につづくヨーロッパは、東方とのちがいがはっきりと示されたという意味で、ペルシア戦役、それも第二次の二年間、を機に生まれた、と言えるのではないかと思う。
勝負は「量」ではなく、「活用」で決まると示したことによって。
(p175-176)
**************************************************************
多分このようなことなのだろうと予想はしていたが、塩野はそれを歴史的事実をできる限り積み上げることで説明している。物語の体裁をとってはいるものの、立派な歴史書たり得ると思う。
(2016年2月18日)