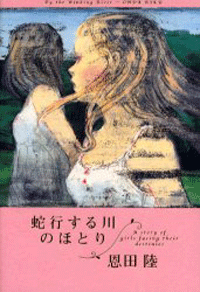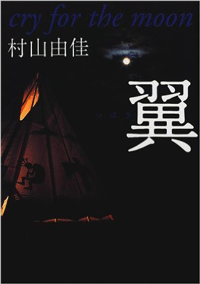恩田陸の『光の帝国 常野物語』(集英社文庫)を読む。
時間を忘れて読んだ。デビュー作『六番目の小夜子』、『蛇行する川のほとり』、そして『球形の季節』と読んでいって、もう恩田陸は私に縁がない作家だから、これ以上この作家の作品を読む必要はないのではないかと思ったが、そうではなかった。少し嬉しい。
常野(とこの)という場所には特殊能力を持った人たちがいる。ある人たちはなんでも記憶することができる。ある人たちは遠い場所の音を正確に聞き分け、何が起きたのかを知ることができる。またある人たちは人の姿を見てその人の未来を読み取ることができる。さらに、ある人たちは心に思っただけで人を一瞬にして焼き殺すことができる。
そのような特殊能力を持った人たちにはありふれた幸福はないものだ。筒井康隆の『七瀬ふたたび』でも超能力者たちは全員抹殺されている。だから、この作品においても、彼らは世界中に散らばって目立たないように暮らしているし、過去には暗い記憶もある。しかし、それでも、彼らにはこれから何かを一族をあげて成し遂げる必要があるらしい。それが語られそうなところで本編は終了した。続編が2冊あるが、読むのを待ちきれない。
恩田陸の学園ものを読むのは苦役に等しかったが、『常野物語』を読んで私の恩田陸評は一変した。ある作家について語るのであれば全集を読んでからにすべしと言ったのは小林秀雄だが、その通りなのだ。
(2015年11月23日)