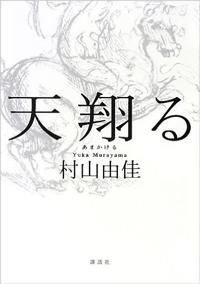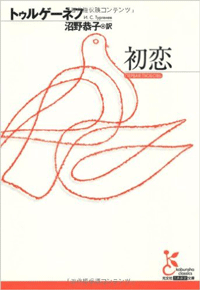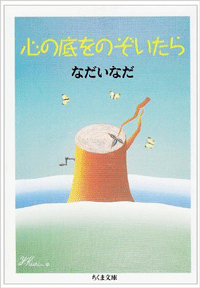村山由佳の『天翔る』(講談社)を読む。400ページを一気に読み切った。
不幸な境遇にいる少女の物語である。母は男を作り家を出た。少女は小学校では父の仕事が鳶職だったためにいじめに遭っていたが、その父は仕事中事故で死ぬ。そんな少女に大人たちが手をさしのべる。だが、その大人たちだって訳ありの人生を送ってきているのだ。少女は不登校になっているが、乗馬の才能があった。やがて彼女は大人たちの支援を得ながら、アメリカで開催される100マイルのレースに出場し、完走するというのが大まかなストーリーだ。
売れっ子作家の作品だけにツボを押さえた作話だ。有り体に書くと、泣かせる。不幸に襲われたのは主人公の少女だけではない。登場人物は誰もが人生の苦難と直面し、それと戦いながら生きている。少女は主人公には違いないが、登場人物たちそれぞれが懸命に生きる姿が描かれている。少女は最後には不幸ではない。そして、懸命に生きてきた周囲の大人も不幸ではない。読者に明るい希望を与える本だ。
(2015年10月25日)