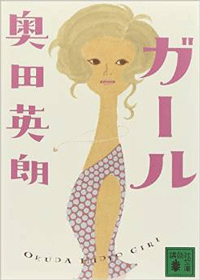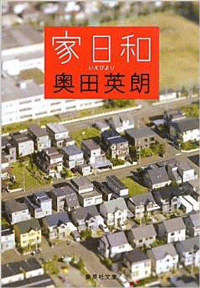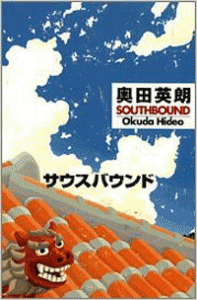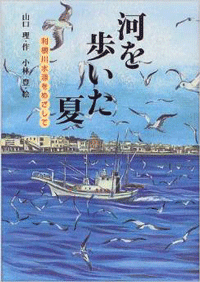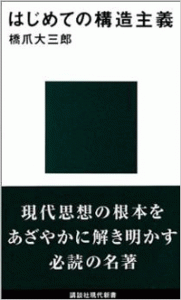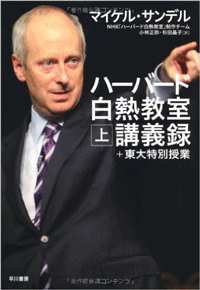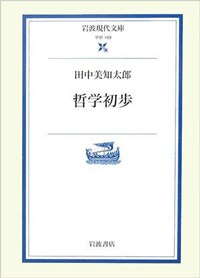田中美知太郎の『哲学初歩』(岩波書店)を読む。
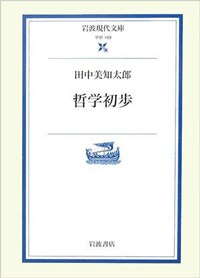
岩波現代文庫に入ったのは2007年だが、底本は1950年に刊行されている。65年も前の本だ。
「哲学とは何か」「哲学は生活の上に何の意味をもっているか」「哲学は学ぶことができるか」「哲学の究極において求められているもの」の4章で構成されている。
読みながら結論が気になったのは「哲学は学ぶことができるか」だ。タイトルからして刺激的である。学ぶことができないという結論になったらどうなるのか。例えば、私はこうして哲学関連書を読んでいるが、この行為は無駄なのだろうか。哲学をもっと学びたいと思って努力してもそれは結局徒労なのだろうか。さらに言えば、世の中にある哲学書は何なのだろうか。学べないならなぜ哲学書があるのか。
田中はプラトンを引用して以下のように述べている。
*******************************************************
プラトンは、哲学の最も大切なところは、自分で見つけ出すよりほかには仕方がないのであって、話したり、書いたりして、これを他に伝えることのできないものであると信じていたようである。そしてこのことを知らずに、それを書物に書いたりする者も、またそういう書物を読んで、何かわかったようなきもちになっている人々も、プラトンはまるで信用しようとしないのである。
*******************************************************
恐ろしいことを平然と言ってのけている。そして、ソクラテスの産婆術について引用した後、こう述べる。
*******************************************************
つまりもし教育というものが、外から知識を授けることではなくて、自分でそれを見いださせることにあるのだとすれば、教師は自分で知識をもっていて、これを外から注入する必要はないのであるから、いっそ余計な知識はもっていないで、人が知識を産み出すのを、わきにいて助ける方がよいわけである。みずから「何も知らない」と言ったソクラテスは、かえってこのような理想的な教師の立場を徹底させていたのだと言うこともできるであろう。
*******************************************************
ここまで読むと結論が見えてくる。田中はこう述べる。
*******************************************************
ソクラテスの産婆術の意味における、教育は可能であり、私たちは問答を通じて、ロゴスによって、人々を知識の想起にまで導くことができるのである。そのかぎりにおいて、智を愛し求める努力も、必ずしも無意味ではなく、プラトンの教育活動も、著作活動も、一概に矛盾であると言ってしまうことはできないであろう。
*******************************************************
これでクリアになった。ただし、やはり部屋に籠もって哲学書を読むことは哲学を学ぶことにはならないのだ。これは肝に銘じておくべきことだろう。
(2015年9月5日)