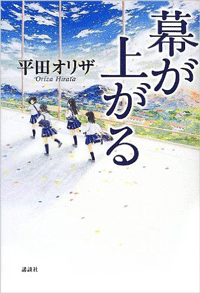本広克行監督の映画『幕が上がる』がDVD化された。主演はももいろクローバーZ。
(左の写真がDVD、右が小説)
原作は演出家の平田オリザ初の長編小説『幕が上がる』(講談社)だ。映画化された時、上映する劇場が近くになかったため私は観ることができなかった。私はしかたなくDVDになるのをずっと待っていたが、DVDを観ていささか落胆した。映画の出来は小説をはるかに下回るものだったからである。
小説にあって、映画にないものが多すぎる。映画にあって小説にないものは殆ど意味不明のエピソードだ。
この作品の原作は演劇がどのようにして作られていくのか、演出とはどういう仕事なのかを描いている。最大の山場は、宮澤賢治の『銀河鉄道の夜』の台本を作る主人公が、谷川俊太郎の『二十億光年の孤独』との出会いによって作品の解釈を一挙に高めるところである。それだけではない。宮澤賢治の詩『告別』も主人公に絶大なインスピレーションを与えるのである。原作では、しがない国語教師の授業が、主人公に大きな影響を及ぼしている。受験間近の教室で、授業は誰もまともに聞いていない。しかし、主人公は退屈そうなその授業から『銀河鉄道の夜』の核心を掴むのである。
こうしたことは、映画では表現しにくいのだろう。重要なシーンであるにもかかわらず、その部分は殆ど映像化されなかった。映画は尻切れトンボになって終わっている。詩の言葉などを映像化することはどのような監督であっても難しいのだろう。それは理解できる。結果的に、映画を観た人も、DVDを見た人も、『幕が上がる』はももいろクローバーZのための映画だとしか認識していないだろう。もったいなさ過ぎる。
子供の頃から映画とその原作の両方を私は知ろうとしてきた。まれに映画化された作品の方が優れていることはある。しかし、殆どの場合、原作の小説を超えることはない。私は映画ファンだし、インターネットの動画もよく見る。映像の力が圧倒的であることを知っている。しかし、それでも映像は活字に勝てないのだ。我々は活字から得られる情報によってひとつの世界を豊かに描き出すことができる。頭の中で作り上げられたそのイメージは映像を凌ぐ。だから活字の世界を完全に映像化するのは無理だ。それでも、努力は不要と言いたいのではない。監督は、言葉を映像に盛り込む努力をもう少ししても良かったのではないか。原作者の平田オリザはこの映画の出来に納得したのだろうか。映像がここまで小説の奥深さに肉薄しようとしなかったことはショックでもある。
(2015年8月9日)