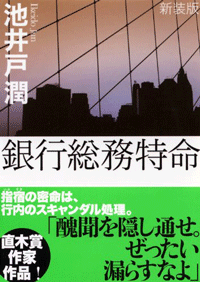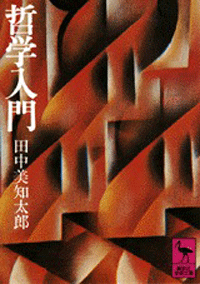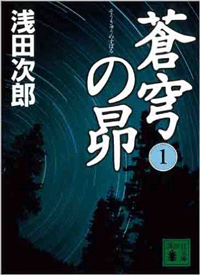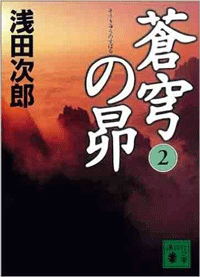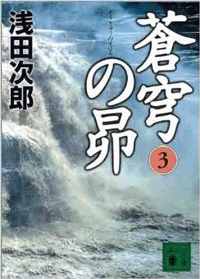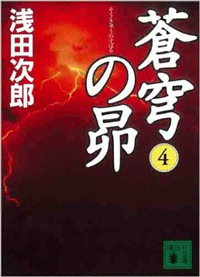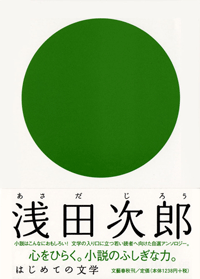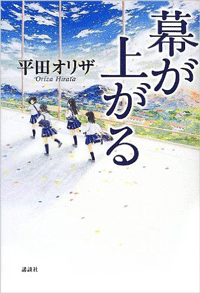池井戸潤の『オレたち花のバブル組』(文春文庫)を読む。
これは『オレたちバブル入行組』の続編である。社内の不正と戦う主人公を描く。前作では半沢直樹が牙をむくようになるまで、妻にやり込められたり、葛藤する場面があったが、こちらの半沢は全く逡巡していない。最初からヴォルテージが上がっている。そうなるとまるでアメリカのヒーロー映画でも観ているような気にさせられる。痛快ではあるのだが、不安や迷いがないキャラクターを見ると、「本当だろうか」という気になる。
むしろ、本作で注目したいのは脇役で登場する銀行員 近藤だ。能力がある人物でありながら、上司に潰され、統合失調症になった彼は銀行から出向させられる。出向先では社長から疎まれ、部下からも横柄な態度を取られる始末だ。それでもその出向先で働かなければならない。卑屈になって生きる彼は、ある日、本来の自分を取り戻し、出向先の悪事を追及し始める。卑屈な自分をかなぐり捨てるシーンに私は喝采を送った。
本作の最終ページには、池井戸潤による言葉が載っている。これはこのシリーズにおける主題だろう。
************************************************
人生は一度しかない。
ふて腐れているだけ、時間の無駄だ。前を見よう、歩き出せ。
どこかに解決策はあるはずだ。
それを信じて進め。
それが、人生だ。
************************************************
(2015年8月29日)