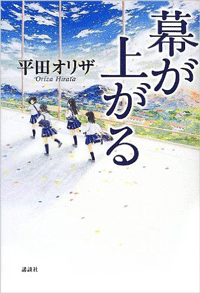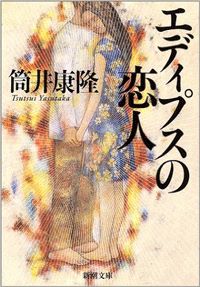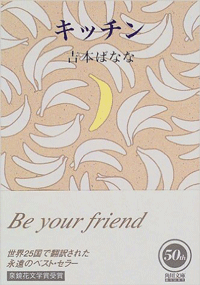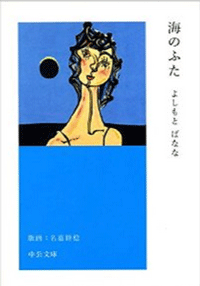浅田次郎の「はじめての文学」(文藝春秋)を読む。
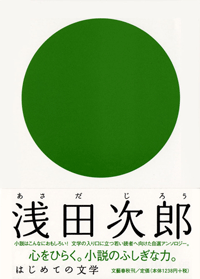
浅田次郎にこのタイトルの作品があるわけではない。文藝春秋社が文学入門として浅田次郎の5作品「ふくちゃんのジャック・ナイフ」「かくれんぼ」「夕暮れ隧道(ずいどう)」「獬(シエ)」「立花新兵衛只今罷越候」を集めて本にしたのだ。
分かりやすい作品が収録されている。極めつけは「夕暮れ隧道(ずいどう)」だ。これはある高校3年生の話である。主人公の男子生徒は、1クラスから15人くらいが東大に入るほどの進学校に通う。彼の前の席にいるのは成績抜群、東大文Ⅰ合格間違いなしの美人だ。彼は授業中、その女子生徒のブラジャーをコンパスの針で外すことに勤しんでいる。ところが、この男子生徒と女子生徒はどういうわけか恋仲になる(いきなりである)。ある日、彼らは海辺に出かける。高校生だし、女子生徒の親は門限を夜7時に設定している。しかし、二人はお互いの下心を確認してラブホテルで一夜を明かすのである。彼らは両家を揺るがす振る舞いをした後、同じ学校のカップルが交通事故で即死したことを知る。
エロスとタナトスというのは隣り合わせであるし、芸術の世界では大きなテーマになる。その意味で浅田次郎の作品は王道をいくものだ。しかし、これが「はじめての文学」? 「はじめて」というのは、小学生向け? 中学生向け? 高校生向け?
他にも、時代劇の撮影に本物の武士が闖入してしまう話を描いた「立花新兵衛只今罷越候」は読み物として面白いが、漫画的すぎないか。
ところが、浅田はそう言い出す教育委員会的な読者のことを想定していたらしい。この本の最後には浅田自身による「小説とは何か」という文章が収録されている。最初の6行にはこうある。
文学とは何か。
文章による芸術表現である。
小説とは何か。
文学のうちの、物語による芸術表現である。
では、芸術とは何か。
人間の営みを含む、天然の人為的再現である。
自作が低俗であるという批判に対して浅田は、「俗」ではあっても「低」ではないという自信はあると反論する。浅田は自作が文学であり、芸術であると確信して「はじめての文学」掲載の5作品を書いたのだ。
(2015年8月11日)